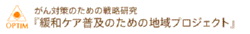緩和ケア用語集 | ||||||||
| 1. | 総論的な言葉 | |||||||
| 1) | WHO健康の定義 | |||||||
| ||||||||
| 2) | QOL | |||||||
| クオリティ ・ オブ ・ ライフ(quality of life)の略。 日本語では「生活の質」の意味。 「その人がこれでいいと思えるような生活の質」 不快に感じることを最大限に軽減し、できるだけその人がこれでいいと思えるような生活が送れるようにすることを目指した考え方。 | ||||||||
| 3) | がん ・ 悪性腫瘍 | |||||||
| からだの細胞が自律性をもって過剰に増えたものを腫瘍といい、これが体に及ぼす影響から良性と悪性に区別される。 特に悪性は、細胞組織から発生しながらも周囲と無関係に増えていき、元の細胞組織を破壊してしまうような現象に基づいて悪性腫瘍とよばれる。 細胞の種類によって上皮組織の細胞から発生するがんと、非上皮性組織の細胞から発生する肉腫とに分けられ、一般的に増殖する速度が速く、またその腫瘍組織が原発部位から離れ、血流やリンパ流による他の部位への転移現象が特徴である。 | ||||||||
| 4) | 緩和ケア | |||||||
| がんやその他の慢性病など、生命を脅かす疾患に対して、疾患にともなって起きる様々なつらさを、それぞれの患者 ・ 家族に合った方法で和らげ、取り除いていくことを目標としたケア。 体のつらさ、こころのつらさ、生活のつらさなど、様々なつらさを抱えたがんなどの患者と家族を総合的に支えること。 | ||||||||
| 5) | ホスピス | |||||||
| ||||||||
| 2. | 主に患者と医療者のやりとりに関する言葉 | |||||||
| 1) | 告知 | |||||||
| 真実を告げ、知らせること。 「告知」という言葉には一方的に医療者から患者側に伝えるニュアンスがあり、「true shearing(真実を分け合う)」などの言葉がかわって使われるようになってきている。 日本人の多くは進行した癌の状態でも真実を知りたいと考えているという意識調査がある。 | ||||||||
| 2) | インフォームドコンセント | |||||||
| 日本語では「説明と同意」と言われる。医療者が病状や治療方針について必要な情報をわかりやすく説明し、患者の理解と納得を得ること。 全ての診療の基本になる考え方。 | ||||||||
| 3) | セカンドオピニオン | |||||||
| 患者が納得する治療法の選択を行うことを目的に、現在治療を受けている主治医以外の他医師(異なる医療機関)の意見を聞くこと。通常は主治医に申し出た上で検査内容や紹介状などを持参して判断を仰ぐ。 主治医に内緒で複数の機関を受診する「ドクターショッピング」や、治療も含めて他の医療機関に紹介する「転院」とは異なる。 | ||||||||
| 4) | リビングウィル | |||||||
| ||||||||
| 5) | がん難民 | |||||||
| 治療方針に悩んだり、治療をしてくれる医師や病院を探し求め、あちこちの医療機関を転々とし、途方に暮れながらさまよっているがん患者たちのこと。 | ||||||||
| 3. | 痛みに関する言葉 | |||||||
| 1) | 疼痛 | |||||||
| 「痛み」のこと。「痛い」と感じる感覚で、体の異常を知らせる最初の徴候であり、生体を保護するために生じる最も多い症状。 7割程度のがん患者で経過中に疼痛が出現するといわれている。 | ||||||||
| 2) | 医療用麻薬 ・ オピオイド | |||||||
| 法律で医療用に使用が許可されている麻薬のことで、オピオイド鎮痛薬ともいう。鎮痛効果の違いによって強オピオイド(「モルヒネ」など)と弱オピオイド(「コデイン」など)の二つに分けられる。代表的な薬は「モルヒネ」「オキシコドン」「フェンタニル」で、適切に使用することによりがんの痛みの治療に大変に有効である。 | ||||||||
| 3) | WHOの除痛のラダー | |||||||
| 鎮痛薬を投与する場合の原則。強さに応じて“階段”のように分けられた「順番」のこと。この順番を基本に痛みの強さに応じて鎮痛薬が選ばれる。 | ||||||||
| * | WHOは鎮痛薬の強さを、非オピオイド、弱オピオイド、強オピオイドの3段階に分けており、この分類が疼痛ケアの鎮痛薬使用の基本となる。 投与方法の基本は ①経口投与を基本とし、 ②患者ごとに適量を求め ③時刻を決めて規則正しく投与して ④副作用を計画的に防止することが重要。 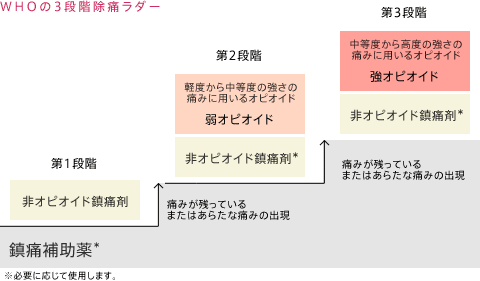
| |||||||
| 4) | モルヒネ | |||||||
| WHO除痛ラダーのステップ3にある強オピオイド(麻薬)。医療用麻薬の代表薬剤。小腸で吸収され、脳に作用し強い鎮痛効果を現す。 がんの痛みの治療に非常に有効で、かつ安全な薬。 | ||||||||
| * | 麻薬中毒になることも、徐々に効かなくなることも、命が縮んでしまうこともない。 | |||||||
| * | 副作用には便秘 ・ 吐き気 ・ 眠気などがあるが対処可能である。 | |||||||
| 5) | 非ステロイド系消炎鎮痛剤(NSAIDs) | |||||||
| 抗炎症作用 ・ 解熱鎮痛作用を発揮する薬剤。鎮痛解熱薬として、がんだけでなく、感冒、関節痛、歯痛などにもよく使用される。 WHO除痛ラダーに基づき、ステップ1に分類され骨や筋肉・腹膜など由来の痛みに有効。 投与方法には、口から、座薬、静脈注射などがある。 副作用として消化器症状(胃潰瘍など) ・ 血圧低下 ・ 腎障害などがある。 | ||||||||
| 4. | 緩和ケアの医療システムに関する言葉 | |||||||
| 1) | 緩和ケア病棟 | |||||||
| (パリアティブケアユニット:PCU)がんに伴うつらい症状の緩和やこころのケア、薬物療法以外の症状緩和ケア等をとおして、患者と家族が最後までできるかぎり希望に添った生活を送れるように、在宅への移行も含めて支援を行う病棟。 2009年4月現在、全国に193施設3770病床あり、山形県では県立中央病院(15病床)と三友堂病院(12病床)の2施設にあります。 | ||||||||
| 2) | 緩和ケアチーム | |||||||
| 一般病院において、緩和ケアを提供するために構成された多職種からなる医療チーム。身体症状の緩和を専門とする医師、精神症状の緩和を専門とする医師、緩和ケアの経験がある看護師や薬剤師などによって構成し、チームで痛みなどの苦痛やつらさの緩和ケアを行う。庄内地域では荘内病院、日本海総合病院などに設置され活動している。 | ||||||||
| 3) | 在宅ホスピス | |||||||
| 終末期にある患者と家族を対象とし、患者の生活の場である家において行われるホスピスケア。多くは訪問診療、訪問看護や訪問介護などを利用して行われる。 患者と家族の意思を尊重し、生活の質(QOL)を高めることを目指す。患者がさまざまな苦痛から解放され、安心して最後までその人らしく生きることを支えるものであり、在宅死を目指しているものではない。 | ||||||||
| 4) | 緩和ケア外来 | |||||||
| 痛みやつらさなどの症状緩和が必要ながん患者や家族に対して、自宅で生活しながら外来通院で療養生活や症状などについて、診察や相談ができる緩和ケア専門の外来。庄内地域では荘内病院、日本海総合病院などに設置され活動している。 | ||||||||
| 5) | ペインクリニック | |||||||
| 疼痛外来ともいう。 痛みを伴う疾患、自律神経疾患などの診断・治療を行う専門分野。 神経炎や神経痛などの神経自体の病変による痛み、悪性腫瘍に伴う痛み、頭痛、血管・循環障害、外傷や手術を原因とする痛み、筋肉・骨格・関節に関する痛みなどが対象となる。 治療法として、神経ブロック、薬物療法(消炎鎮痛薬・麻薬・麻薬拮抗性鎮痛薬・抗けいれん薬・鎮静薬・抗精神薬)、東洋医学(漢方・鍼)、刺激的除痛法などが用いられる。 悪性腫瘍に伴う疼痛対策は緩和ケアの一部をなし、生活の質(QOL)の面からも十分な鎮痛が望ましく、モルヒネをはじめとするオピオイド製剤が多用されている。 庄内地域では、日本海総合病院に設置されている。通常は再来が対象だが、医師の紹介があれば受け入れることもある(要相談)。 荘内病院では2009年4月現在準備中。 | ||||||||
| 5. | 緩和ケアにかかわる福祉サービスに関する言葉 | |||||||
| 1) | 介護保険 | |||||||
| 社会の高齢化に対応するために創設された社会保険方式による公的な介護制度。1997年に公布された介護保険法により2000年4月から施行された。 保険者は市町村及び特別区であり、被保険者は市町村に住所がある①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)である。第1号被保険者の介護保険料は個別徴収と年金からの天引き、第2号被保険者の介護保険料は医療保険の一般保険料とともに徴収される。 介護保険法の附則に基づき介護保険実施5年目の見直しによる法律の一部が改訂され、2006年4月より軽度者(要支援・要介護1)に対して、自立支援を徹底する「新たな予防給付」が開始された。 さらに、2009年4月より要介護認定の調査方法見直しがされている。 末期がんは40歳以上からサービスを受けることができる。 | ||||||||
| 2) | デイサービス・デイケア・療養型通所介護 | |||||||
| ■デイサービス:通所介護 老人福祉法に基づき、原則として65歳以上の在宅の虚弱高齢者や寝たきり高齢者を、老人デイサービスセンターに送迎し、健康チェック、入浴、給食など日常生活サービスを提供する通所事業。 | ||||||||
| ■デイケア:通所リハビリテーション 慢性疾患患者および心身症患者、精神障害者が社会復帰するための制度の一環。昼間だけそれぞれの医療施設で治療をうけ、夜間は自宅へ戻って療養生活を送る制度をいう。病院と家とを交互に往来させることにより治療と社会性の回復を目指す。 | ||||||||
| ■療養型通所介護 2006年4月の介護報酬改訂時に新設された通所介護の一類型。神経難病や末期がん、重度の脳血管障害者など医療と介護を併せもつ中重度の在宅療養患者とその介護者の支援を目指すもの。 常に看護師による観察が必要なこれらの在宅療養者が日中通うことで必要な看護や療養サービスを受けることができるよう従来の通所介護(デイサービス)に加えられ在宅中重度者地域で支え、家族の負担軽減につながると期待されている。 | ||||||||
| 3) | 訪問看護 | |||||||
| 在宅の療養者および障害者を対象として健康の回復・維持や、在宅療養の援助(病気を持っていてもなるべく在宅で生活できるように)、平安な死への援助など、対象者の自立と生活の質(QOL)の向上を目指す看護活動であり、在宅療養者とその家族の生活を支援する有効な手段の一つである。在宅療養では、対象者の生活の場において、治療的ケアから回復期のリハビリテーションおよび終末期のケアまで、長期にわたる幅広い看護が求められる。訪問看護においては、対象者の自己決定を尊重し、療養者を介護する家族を支援することが重要である。介護保険が創設されて以来、訪問看護は保険制度に基づく居宅サービスとして利用されている。がん末期の場合、医療依存度が高くなる為医療保険を使用する場合が多い。 | ||||||||
| 4) | 訪問介護 | |||||||
| ホームヘルプサービスのこと。 ホームヘルパーが要介護者の居宅を訪問して入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの家事、日常生活の世話、相談、助言を行うサービス。 | ||||||||
| 5) | 移動入浴サービス | |||||||
| 高齢や障害により家庭のお風呂に入ることができない方に対して、訪問入浴の専門スタッフが浴槽を持ってご自宅へお伺いし、寝たまま入浴できるサービス。 | ||||||||
| 6. | がんの進行度に関わる言葉 | |||||||
| 1) | 早期がん | |||||||
| 一般に、進行がんや末期がんに対して、発生後まもない進行の度合いのきわめて小さいがんをいう。早期がんの定義は発生部位やがんの種類によって異なる。例えば早期胃がんは、がんが粘膜層および粘膜下層のとどまるものと消化器内視鏡学会で定義されている。 | ||||||||
| 2) | 進行がん | |||||||
| 早期がんと対比して用いられる言葉で、がんが進行していることを示す表現。早期がん以外のがんの総称であり、治療によって根治が可能なものも含まれる。しかし、一般的にはがんが原発巣からほかの臓器やリンパ節に転移した状態や、治癒が不可能で余命が限られている状態という意味でも用いられる。 | ||||||||
| 3) | 末期がん | |||||||
| 進行がんの中でも病気がすすみ、余命が6ヶ月以内と考えられる時期のがん。その多くに種々の不快な症状が伴うため、苦痛を取り除くための緩和ケアが行われる。 | ||||||||
| 4) | 転移 | |||||||
| 腫瘍(がんなど)細胞の生体内での広がり方の一形態。 腫瘍細胞が体液(血液やリンパ液)とともに移行し、原発巣(もともと発生した臓器)から離れた部位で同一の腫瘍を形成することをいう。血流により他の組織・臓器に達する血行性転移と、リンパ流によりリンパ節に達するリンパ行性転移とがある。 | ||||||||
| 5) | 再燃・再発 | |||||||
| 一度治癒していた病気が再び出現することをいう。 がんの再発とは、治療されて一旦治癒したかに見えた病変が、再び増殖することで、もともとの病変部位で再悪化する局所再発と新に転移をおこす転移再発がある。 | ||||||||
 |  |
 |  |
|
|
 |  |
 |  |